久々に日本映画らしい映画を観た。
昨日見た「劔岳」や「鳥刺し」も日本映画らしいと言えば日本映画らしいのだが,ここでの日本映画はもっと狭義の「日本映画」。
ある時期(たぶん,70 年代から 80 年代初めにかけて)の日本映画には,独特の匂いがあったように思う。湿ったアスファルトや土の匂いだったり,木造アパートのカビ臭い匂いだったり,煙草や安物の化粧品の匂いだったり,生き物としての人間が放つ有機的な匂いだったり…
今日は日本映画祭で根岸吉太郎監督の「ヴィヨンの妻」を観た。太宰治の同名小説を柱に,他の太宰作品のエッセンスを加えて 1 本の映画に仕上げている。主演は松たか子と浅野忠信。厭世的で,死にたいのに死に切れないダメ人間の夫と,楽天的で明るく芯の強い妻。こういうラブストーリーもあるのか,と思わせる。ラストで象徴されるように,二人はあまり互いのことを見ない。対面せざるを得ない留置所のシーン,ここで妻は唯一,悲しみの感情を高ぶらせる。ここを境に,ラストに向かって物語を進める根岸演出も確かで隙がない。よくできた映画だ。
でも,僕が一番唸ったのは,スクリーンに映った演技や映像ではなく,物理的にはスクリーンから伝わるはずのない「匂い」だ。「かおり」じゃなく「におい」。主人公の大谷は「死にたい」と連発し,実際心中未遂もするのだが,スクリーンからは死の匂いではなく,むしろ生の匂いがプンプンしてくる。これはかつての日本映画が持っていた独特な匂いだと思う。冒頭に述べたような湿っぽい雨の匂い,安酒場の煮込みの匂い,そして人間自身が放つ「生」の匂い,これはそこはかと漂うエロスの匂いでもある(見せないエロチシズムも,ある意味,日本映画の宝だと思う)。そう,この映画から感じる匂いは,「生の匂い」と言っても,ヴィヴィッドで明るい朗らかさを感じさせるような匂いではない。それは死と背中合わせになった生の匂いだ。何というか,相転移における臨界点に位置するような…そうか,その意味では「生の匂い」であり,かつ「死の匂い」であるわけだ。「死を見据えた生の匂い」とでもいうべきか。その意味で,この作品からこの匂いを感じるのは必然なのかもしれない。
物語では時折「死の予感」を漂わせながら,ラストはすがすがしいような「生」を感じさせる。表層的な死生観と対照的な「生の匂い」。その振幅の大きさ,ダイナミズムがこの映画の魅力と言えるんじゃないだろうか。
人は誰しもが生きていながら,それは同時に死への道行きでもあるわけだ。「死ぬことは生きることだ」とは誰の言葉だったか?そういえば,太宰好きで知られる宮本浩次も「敗北と死に至る道が生活ならば~」と唄っていたっけ。
そうそう,帝都東京の中心から少し離れた生活圏へと走る中央線が,またこの独特な匂いを増幅しているようにも思えた。
うーん,こっちに住んでて日本料理を食べたくなることはあまりなかったんだけど…踏切沿いの酒場の煮込みが少し恋しくなったなぁ…あと 4 ヶ月は辛抱しないとなぁ…
追記: …と,一通り書き上げて,自分で読み直してみたら,RC サクセションの「いい事ばかりはありゃしない」が聴きたくなった。というわけで,ちょい聴いて,そいで今日は寝ます。
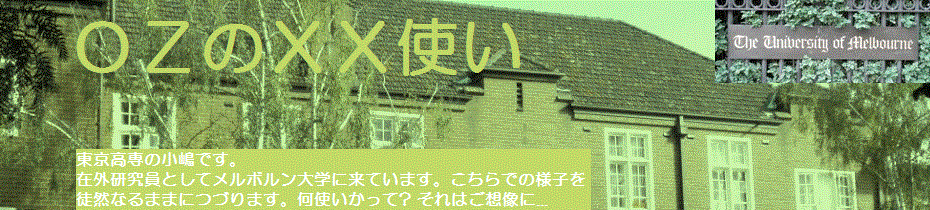
0 件のコメント:
コメントを投稿